お役立ちコラム
台湾の小売店/量販店で日本食品を取引するには?担当者が最初にぶつかる壁と突破口
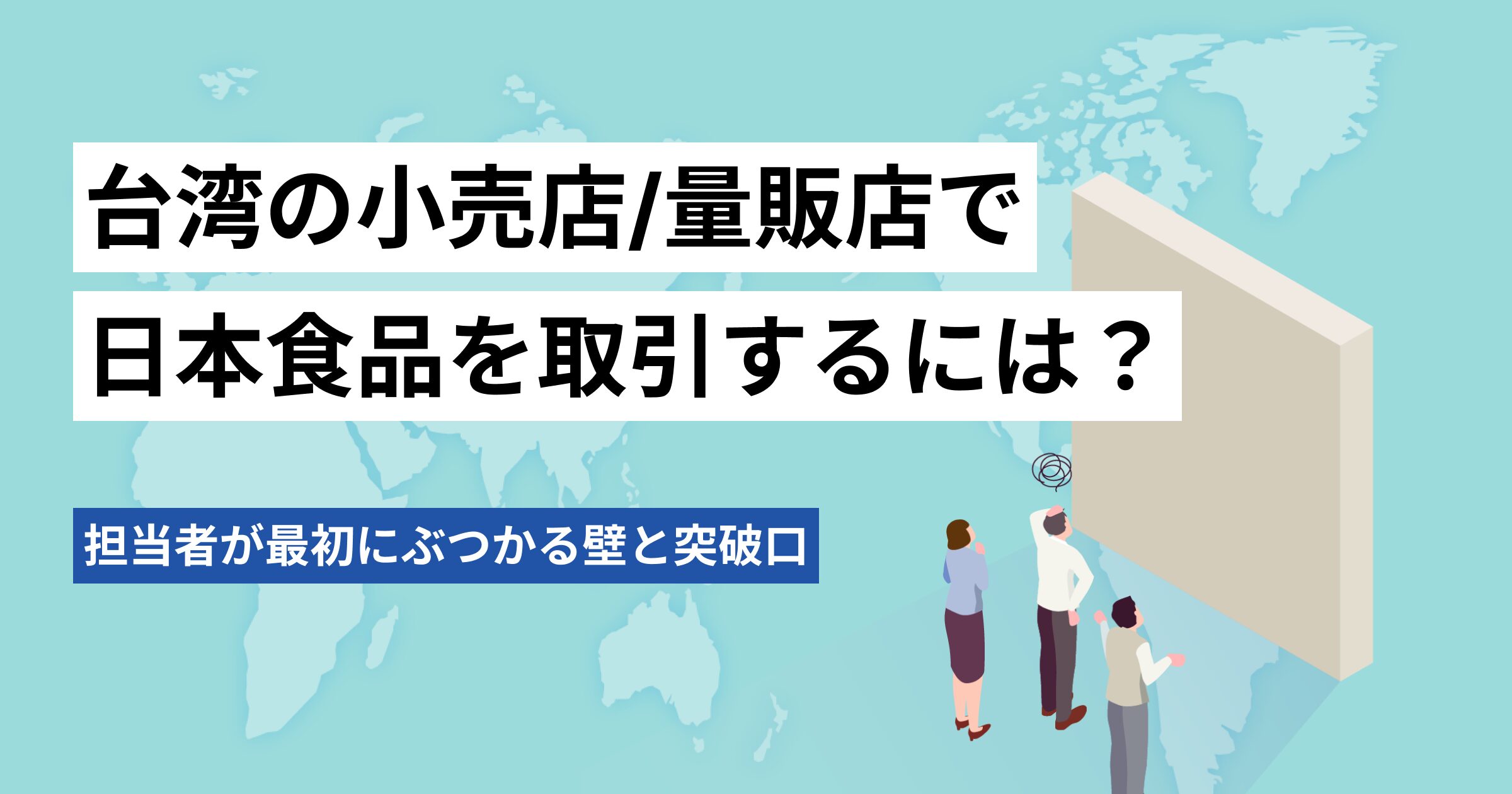
「台湾の売場に日本食品を並べたい」
そう思ったとき、最初にぶつかるのは「どうすれば取引につながるのか」という壁ではないでしょうか。
いい商品を持っていても、現地の小売店や量販店は冷静に条件を見ているため、戦略と緻密な計画が必要となります。
この記事では、台湾の小売担当者が求める視点や、輸出で立ちはだかる規制、棚取り交渉のリアルな進め方までをまとめています。
初めて動き出す人でもイメージしやすいように、準備の具体例や支援の活用法まで参考にしてください。
台湾の小売店/量販店が日本食品に求めている条件とは
現地で人気のある日本食品ですが、ただ「日本製だから」という理由だけでは取引は進みにくくなっています。
実際に棚を任されるバイヤーは、数字や安定供給といった現実的な条件を重視します。
「日本製だから売れる」は過去の話
かつては「日本産=品質の高さ」で棚が空く時代もありました。
今は韓国ブランドや欧米ブランドも勢力を伸ばしており、ローカル商品との競争も激しいのが実情です。
日本製であることは強みの一つですが、それだけでは差別化につながりにくいのです。
現地消費者の購買動機(健康志向・ギフト需要・SNS映え)
台湾の消費者が日本食品を選ぶ理由はさまざまです。
- 健康志向:低糖・低塩・無添加・高たんぱくといった明確な表示が支持される
- ギフト需要:中秋節や旧正月など、季節イベントに合わせたパッケージや個包装が重宝される
- SNS映え:色や形の美しさ、開封時の体験がシェアを後押しする
どの購買動機を狙うかによって、商品開発や販促の打ち出し方が変わります。
小売店/量販店担当者が確認するチェックポイント
バイヤーが商談で必ず確認するのは次のようなポイントです。
| チェック項目 | 内容例 |
| 価格帯 | 店頭価格レンジ・粗利率・販促費の負担割合 |
| 供給安定性 | 月ごとの発注単位・リードタイム・欠品時の代替提案 |
| 規格対応 | ケース入数・賞味期限残日数・JANコードの有無 |
ここを数字で答えられないと、せっかくの魅力的な商品でも交渉は前に進まないこともあります。数値による説明ができるように、しっかりと準備しましょう。
初めての輸出で立ちはだかる規制と実務負担
販路を考える前に、輸出に必要な規制や事務作業を整理しておく必要があります。
ちょっとした抜け漏れが、通関で止まる原因になるためです。
成分表示やラベル表記のローカライズ問題
台湾では、繁体字での表示が求められます。
商品名・原材料・原産国・賞味期限など、細かく決められたフォーマットがあります。
外貼りシールでの対応も可能ですが、剥がれや印字不良はクレームにつながるため要注意です。
輸入検査・通関で止まる理由
輸入でつまずく典型的な理由は次の通りです。
- HSコード(関税分類)の誤り
- 成分証明や衛生証明の不足
- 製造所の表記ミスや揺れ
小さなことに見えても、現地では出荷停止につながることがあります。
事前に要件を確認し、必要書類をそろえる準備が欠かせません。
小ロット輸出でも発生するコスト
「少量だから安く済む」と思われがちですが、翻訳やラベル印刷、通関手数料といった固定費はロット数に関係なく発生します。
冷蔵や冷凍の物流を使うと、資材や温度管理費も追加されます。
テスト販売では、常温で扱える商品からスタートするのが現実的です。
台湾小売店/量販店での棚取り交渉をどう進めるか
商品説明をするだけでは棚は取れません。
バイヤーが見ているのは「売場でどう回るか」という仕組みです。
発注単位や取引条件を把握しておく
ケース入数や最小出荷量を理解していないと、交渉の段階で信頼を失います。
また、店頭価格から逆算した粗利の構成を示し、販促費の分担についても最初から話しておくことが重要です。
「試しに置いてみよう」と言わせるサンプル戦略
バイヤーの背中を押す一言は「まず試してみるか」。
そのために用意するサンプルは、規格品に近い状態で渡すのが基本です。
一口で違いがわかる味や香りを示し、売場での使用シーンを想起させる工夫が有効です。
支払サイト・返品条件など異なる商習慣
台湾では支払サイト(締め日から支払いまでの期間)は店舗によって違います。
返品条件も日本の感覚とは異なり、期限や破損条件は契約書で明記しておく必要があります。
値引き後の返品といった二重負担を避ける工夫も欠かせません。
展示会か?代理店か?それとも別ルートか?
台湾市場での入り口はひとつではありません。
展示会出展、代理店経由、直接交渉など、どのルートを選ぶかは目的次第です。
展示会出展は本当に成果につながるのか
展示会は一度に多くのバイヤーと接点を持てるのが強みです。
ただし、会期中の反応が良くても在庫や供給体制が整っていなければ契約には至りません。
出展を検討する際は、展示後のフォロー体制まで含めて計画する必要があります。
代理店任せにすると起こりやすい失敗
代理店に任せきりにすると、現地の声が自社に届かなくなりがちです。
価格と在庫だけのやりとりになり、商品改善や販促の軌道修正が遅れることもあります。
任せる範囲を明確にし、定期的な報告体制を作ることが重要です。
成功事例に共通するのは現地バイヤーとの直接接点
取引がうまくいく企業に共通しているのは、現地バイヤーと直接話す機会を作っていることです。
意思決定者の基準をその場で確認できれば、交渉の精度が一気に高まります。
棚全体をどう作るか、隣接カテゴリーとの相性まで話せると信頼につながります。
中小食品メーカーが取引を実現するために必要な準備
準備の質が交渉の深さを決めます。
台湾市場に合わせて「翻訳」した強みを示すことが大切です。
「自社商品の強み」を台湾市場用に翻訳する
言葉だけでなく、魅力に感じるポイントをおさえた上で、台湾市場に響く内容に変換してあげる必要があります。
- 産地や製法の物語は、日本語のままでは伝わりにくい場合があります。
- 健康や安全、ギフト需要といった台湾の購買動機に置き換える。
- 数値や使用シーンを添えることで納得感が高まります。
小ロットから始めるための価格・物流の試算
価格設定は店頭価格から逆算するのが基本。
輸送費や関税、販促費を含めた粗利表を作成し、欠品と廃棄のどちらを優先するかという判断軸を持つこと。
常温の混載便を想定し、在庫回転のモデルを複数用意しておくと安心です。
現地に行かずにできる情報収集と商談
現地に行かなくてもできることは意外と多いです。
小売店のチラシやECサイトの売れ筋ランキングから、価格帯やSKU構成を把握できる。
オンラインでの試食会や、店舗スタッフ向けの簡易マニュアルの提供も有効です。
支援パートナーを活用するという選択肢
すべてを自社で抱え込むと、時間もコストもかかります。
支援パートナーを活用することで、遠回りを減らすことができます。
規制・商習慣・人脈をショートカットする価値
- 通関で止まりやすいポイントを事前に潰せる
- 現地向け販促資料を最初から利用できる
- 担当者が商談に集中できる環境を整えられる
実績を持つ支援企業がもたらす安心感
実績ある支援企業なら、棚取りから補充発注、クレーム対応まで流れを想定してサポートしてくれるケースもあります。
現地の販促カレンダーを前提に計画できる点も大きな安心材料です。
自社だけで抱え込まない方が結果的に早く安く進む
学習コストを自社で負担するより、外部の知見を取り入れた方が断然効率的。
初回のつまずきを避け、スピードと再現性を両立できます。
台湾市場での競争力は、その積み重ねから生まれます。
まとめ
台湾の小売店との取引を実現するには、日本市場の感覚をそのまま持ち込んでも通用しません。
価格・供給・規格という基本を揃え、規制や通関を事前にクリアにしておくこと。
そして、支援パートナーをうまく活用しながら小さく試すことです。
「日本製だから売れる」という時代は終わっています。
現地の目線に立ち、数字と仕組みで語れるかどうかが突破口になるので、専門家と一緒に「届く戦略」を考えてみてください。東西食品は台湾を中心としたアジアへの百貨店催事のプロです。
商品特徴を理解した上で、効果的な出展サポートをいたします。
相談は無料、まずはお気軽にお問い合わせください。
