お役立ちコラム
食品メーカーが補助金を味方に「海外進出」に挑戦する方法を解説。資金計画と落とし穴も。
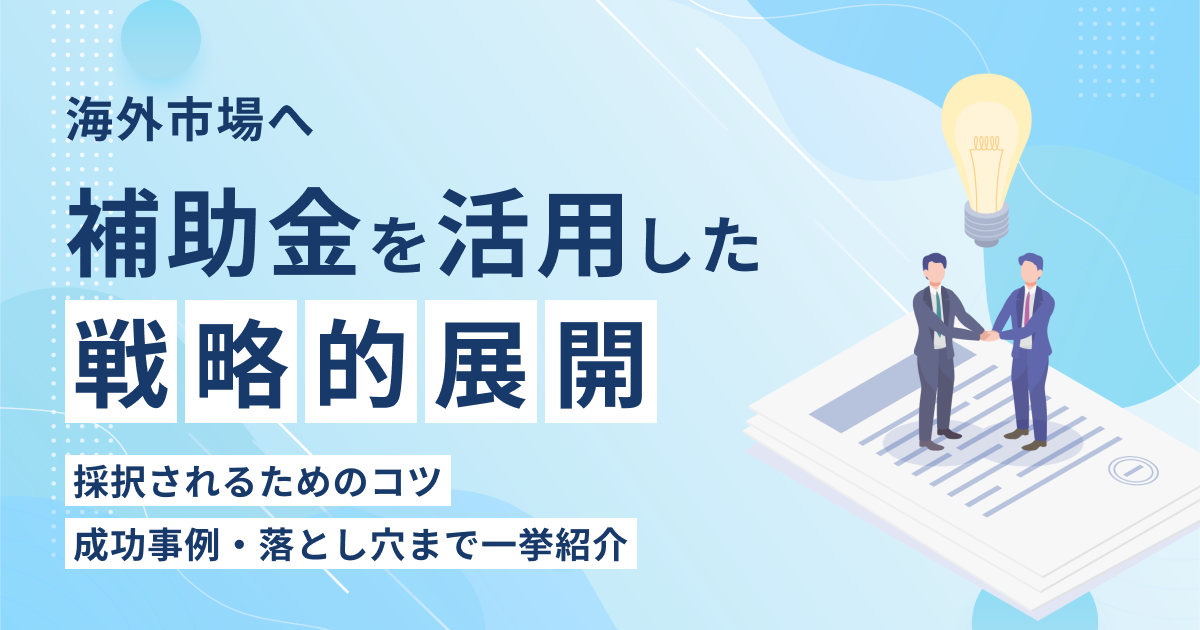
国内の市場に限界を感じ、ふと「海外でも売れるのでは」と思ったことはありませんか。
とくにアジア圏では日本の食品が高く評価されており、百貨店催事やオンライン販売などを通じて人気を集めています。
ですが、いざ海外進出を検討しようとすると、思った以上にハードルが高いのも事実です。
輸送や表示対応、現地販売の方法やパートナー選定。
そして、何より悩ましいのが「最初の資金をどう確保するか」ではないでしょうか。
そんなときに頼れるのが、国の補助金です。
旅費や出展費、検査対応などを含め、海外展開にかかる費用の一部を支援してくれる制度が整備されてきています。
この記事では、2025年時点で活用できる国の制度を中心に、補助金の概要とメリット、気をつけたいポイントまでをわかりやすく整理していきます。
「まずは試してみたい」という方にこそ、知っておいていただきたい内容です。
補助金を申請する目的
補助金は、単に資金を受け取ることが目的ではなく、「やってみたいけど、資金面で踏み出せない」という企業へ将来的な売上増加や販路の拡大、新たな事業成長のきっかけとして活用するものです。
とくに海外展開では、未知の市場に挑む不安もあります。
だからこそ、旅費やブース出展費用、翻訳・現地仕様への対応などにかかる費用を国が一部負担することで、企業が「最初の一歩」を踏み出せるよう設計されています。
食品業界向け海外進出補助金とは。
国内需要の頭打ちと公的支援拡充の背景
日本国内の食品需要は、少子高齢化や健康志向の変化により横ばいが続いています。
一方で、台湾や香港、シンガポールなどでは日本食への関心が根強く、現地での販売に手応えを感じる企業も増えています。
農林水産省も、2030年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円に引き上げる目標を掲げています。
その流れのなかで、輸出のハードルになりがちな「規制対応」「販路開拓」「物流」などに対する支援制度が充実してきました。
とくに、展示会出展や翻訳、ラベル対応など、初期費用がかかりがちな部分に対して補助金を活用できるのが、今の大きな特徴です。
補助金活用で得られる3つのメリット
自己資金リスクを抑えながら海外でテストマーケティングできる
「まずは出してみたいけれど、何百万円も先に投資するのは不安」。
そんな方にとって、補助金の最大のメリットは“初期コストの圧縮”です。
たとえば、150万円かかる展示会出展に対して補助率が2/3であれば、自己負担は50万円。
旅費や輸送費も含めて支援対象になる場合、かなり実現しやすくなります。
失敗のリスクを抑えながら、実際の現地反応をテストできるという意味でも、補助金は頼れる存在です。
専門家派遣・販路支援で社内リソースを節約
海外進出は、通関や法規制、契約書対応など、専門知識を要する作業が多く発生します。
そこで役立つのが、JETROや外部支援機関が提供する「コンソーシアム型支援」です。物流や販促まわりを一括で請け負ってもらえることで、社内では製品づくりや既存業務に集中できます。
結果として、人的リソースを大きく割かずに済むのも見逃せないメリットです。
採択実績が金融機関・取引先への信頼材料に
「国の補助金が採択された」という実績は、社外に対する大きな信頼材料になります。
とくに金融機関や商社、現地パートナーとの交渉時には、その信用が後押しになることも。
将来的に投資を受けたり、販路を広げたりするときにも、補助金の採択は有利に働きます。
補助金3選(要件・補助率・2025年スケジュール)
ものづくり補助金〈グローバル展開型・第20次〉
中小企業の海外展開を後押しする制度として、もっとも広く知られているのが「ものづくり補助金」です。
その中でもグローバル展開型は、輸出や海外販路開拓に特化した内容になっています。
現在公募されているのは「第20次公募」。
2025年7月1日から申請受付が始まり、締切は7月25日です。
補助上限額は最大3,000万円。
補助率は中小企業で1/2、小規模事業者は2/3と手厚く、海外展示会の出展費や旅費、通訳・翻訳費も対象に含まれます。食品製造業も対象業種として明記されており、採択実績も多数。
jGrantsを通じた電子申請が必須なので、事前のgBizID発行は忘れずに行っておきましょう。
【公募要領・詳細】
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
農林水産省「輸出環境整備推進事業(規制対応支援)」
食品の輸出にあたっては、国や地域ごとの規制・認証対応が避けて通れません。
たとえば「原材料の証明書」や「現地語のラベル対応」「衛生基準の認証」などです。
そうした“輸出前の壁”を取り除くために用意されているのが、農林水産省の「輸出環境整備推進事業」です。
補助対象となるのは、以下のような取り組みです。
・HACCP、ハラール、ISO22000などの認証取得
・輸出先国に合わせたラベル・表示対応
・残留農薬、衛生検査などに関する調査・書類作成
2025年は7月時点で第3次公募が終了し、秋にかけて第4次公募が予定されています。
事業内容によって補助金額は異なりますが、数百万円〜数千万円の規模で実施されてきた実績があります。
単独での申請だけでなく、複数企業による連携プロジェクトとしても活用可能です。
JETRO「中堅・中小企業輸出支援エコシステム形成事業」
販路開拓や現地プロモーションを強化したい場合に活用したいのが、JETROによる「エコシステム形成事業」です。
この事業は、企業単独での申請ではなく「民間支援事業者(例:広告会社・物流企業など)」とJETROが連携したプロジェクトの一員として参加する仕組みです。
・現地物流の構築
・通関や食品規制対応の代行
・越境ECやSNSプロモーション
といった幅広い支援を、事業者側が提供するなかで、参加企業は必要なサービスを選び、補助対象として活用できます。
2024年度は5月末に1次公募が終了しており、JETROは公式に「秋以降に2次募集を検討中」と発表しています。
補助上限は最大2,000万円、補助率は1/2。事業者とのマッチング次第で、手離れのよい支援を受けられるのが特徴です。
補助金活用のデメリットとリスク対策
補助金は便利な制度ですが、「もらえるから」と安易に活用するのは危険です。
実行にはそれなりの準備と負担もあるため、あらかじめリスクを知っておくことが大切です。
自己資金立替と資金ショート対策
補助金の大半は「後払い」方式。
つまり、いったんすべての経費を自己資金で立て替え、事業完了後に精算される流れです。
たとえば100万円の補助を受ける場合、150万円〜200万円程度をいったん支払う必要があります。
実際には、「想定より入金が遅れた」「展示会直前で急な追加費用が出た」といったケースも多く、資金繰りを甘く見ていると危険です。
対策としては、金融機関のつなぎ融資や補助金専用の短期資金枠を確保しておくと安心です。
書類作成・実績報告にかかる人的コスト
補助金は「申請したら終わり」ではありません。
交付決定後も、事業計画・経費証明・実績報告など、提出すべき書類が続きます。
とくに初めての申請では、どの経費が対象か/領収書はどの時点のものが有効かといった細かい判断に時間を取られがちです。
社内に経理や法務の担当者がいない場合は、外部の専門家(中小企業診断士などの補助金コンサル)に一部だけでも依頼すると、ミスや負担を減らせます。
補助対象外経費・為替変動リスクを織り込む方法
補助金の対象外になる経費も少なくありません。
たとえば以下のような費用は、制度によっては補助対象から外れることがあります。
- 催事販売スタッフの日当・手当
- 為替変動による損失
- 飲食や接待に類する経費
また、海外での取引になると為替リスクもつきものです。
想定より円安が進むと、実質的な支出が増えるケースもあります。
こうした「見えないコスト」もあらかじめ計画に含めておくことが、持続的な事業の第一歩です。
申請から実行までのアクション
補助金は、「申請がゴール」ではありません。
採択されたあとも、出展準備・現地対応・実績報告など、やることは少なくありません。
全体を通しておおよそ1年間のプロジェクトと考え、スケジュールを立てておくと安心です。
公募開始〜採択:3か月でやるべき準備
補助金の公募は年に数回あるものの、応募から採択までは早くても数か月かかります。
そのため、制度が出てから準備するのではなく、「出そうと思ったらすぐ出せる」ようにしておくのが理想です。
具体的には、以下のような項目をあらかじめ整理しておくとスムーズです。
- 輸出したい商品の一覧とスペック
- 想定する国・販路(展示会かECか)
- 想定経費と見積もり(旅費、翻訳、出展料など)
- 売上やブランディングなど、期待する効果
最初からすべてを完璧に書く必要はありません。
けれども、支援実績のあるパートナー企業と相談しながら設計すると、無理のない計画になります。
実行・実績報告:経費精算と成果測定の注意点
採択された後は、計画通りに事業を実行し、その後「実績報告書」を提出する必要があります。
これには、使った経費の領収書や出展時の写真、売上レポートなどが必要です。
一つでも証拠が足りないと、その分の補助金が支払われない場合もあるため注意が必要です。
また、補助金を受けたからといって、必ずすぐに売上が伸びるわけではありません。
重要なのは、「検証できたかどうか」です。
現地の反応や客層、売れ筋などを丁寧にまとめておくと、次回以降の申請や改善にもつながります。
海外販路を持続拡大するマーケティング戦略
「一度出展して終わり」では、せっかくの投資がもったいないもの。
補助金をきっかけに、海外との継続的な接点を持てるようにしておくことが、今後の事業に効いてきます。
越境ECと現地ECでファンを育てる導線
出展後に「購入できる場所」があることは、お客様にとっても大きな安心になります。
最近はShopifyなどを活用した越境ECや、現地の大手ECモールに出品する食品メーカーも増えています。
販促の中心をイベントにしつつ、日常的にはECで購入してもらう導線があると、売上の安定につながります。
ディストリビューター/リテールチェーンとの契約モデル
一部の企業は、現地のディストリビューター(卸商社)や小売チェーンと提携し、BtoB取引を強化しています。
百貨店の催事が「お試し」の場として機能し、その後、棚取りや定番化につながるケースもあります。
ただし、条件交渉や契約まわりは、言語や商習慣の壁も大きいため、実績のあるパートナーと動くのが安心です。
SNS・KOL・展示会を掛け合わせた認知拡大
催事やECとあわせて、現地SNSでの発信も効果的です。
とくにインスタグラムやFacebookなどのSNSでのインフルエンサー活用は、食品ジャンルとの相性が良く、短期でも反応が得られやすい傾向があります。
出展やテスト販売の際は、SNS投稿やライブ配信と連動させて、購入導線までの「導き方」を設計しておくとよいでしょう。
組織と資金繰りを整える(長期的な海外事業基盤づくり)
補助金を使った海外展開は、「1回限りの挑戦」ではなく、「継続的な事業」へと育てていくのが理想です。
そのためには、最初の挑戦段階から、少しずつ社内外の体制を整えておくことが大切です。
輸出専任チームと外部パートナーの役割分担
最初から社内に貿易担当や多言語対応ができる人材がいる必要はありません。
ですが、「誰が外部との窓口になるのか」「どの業務をアウトソースするのか」は明確にしておきたいところです。
翻訳やSNS運用、催事運営など、現地対応が必要な業務は、専門パートナーに任せることで、成功確率が大きく変わってきます。
実際、百貨店での催事出展などは、独自で動くよりも、実績のある支援企業と連携したほうが、出展枠や集客、販売設計の面で有利になることが多くあります。
つなぎ融資・貿易保険・ヘッジでキャッシュを守る
補助金は便利ですが、「もらえるまでに時間がかかる」ことは忘れてはいけません。
申請〜実行〜精算までには半年以上かかることもあり、その間の運転資金をどう確保するかは大きな課題です。
信金・地銀などの“つなぎ融資”や、売上債権を守る貿易保険の活用など、資金繰りの工夫も並行して進めておくと安心です。
国際会計・内部統制を先回りで整備
海外売上が一定規模を超えると、現地との会計処理や税務対応も発生してきます。
とはいえ、最初の段階ではそこまで準備する必要はありません。
ただ、現地口座の開設や通貨の管理、インボイスの発行フローなど、「いずれ必要になるもの」を事前に知っておくことで、次の一歩がスムーズになります。
社内に専門人材がいない場合は、最初から外部専門家とつながっておくと安心です。
まとめ
補助金を活用すれば、海外展開の初期コストを抑えながら、安全に「試してみる」ことができます。
ただし、準備には時間がかかり、自己資金や社内体制、外部との連携など、事前に整えておくべきことも多くあります。
特に、展示会や催事出展のように「現地での販売」が必要な場面では、支援実績のあるパートナーと組むことが、成功の近道になります。
もし「台湾の百貨店でまずは反応を見てみたい」とお考えであれば、催事企画から物流・通訳手配、販売サポートまで含めて支援できる私たちのような存在に、ぜひ一度ご相談ください。
無理なく、着実に。
補助金を味方に、海外という次のステージを一緒に目指していきましょう。
