お役立ちコラム
海外食品の販路を広げるSNSマーケティング戦略。現場担当者が知るべきリアルとは?
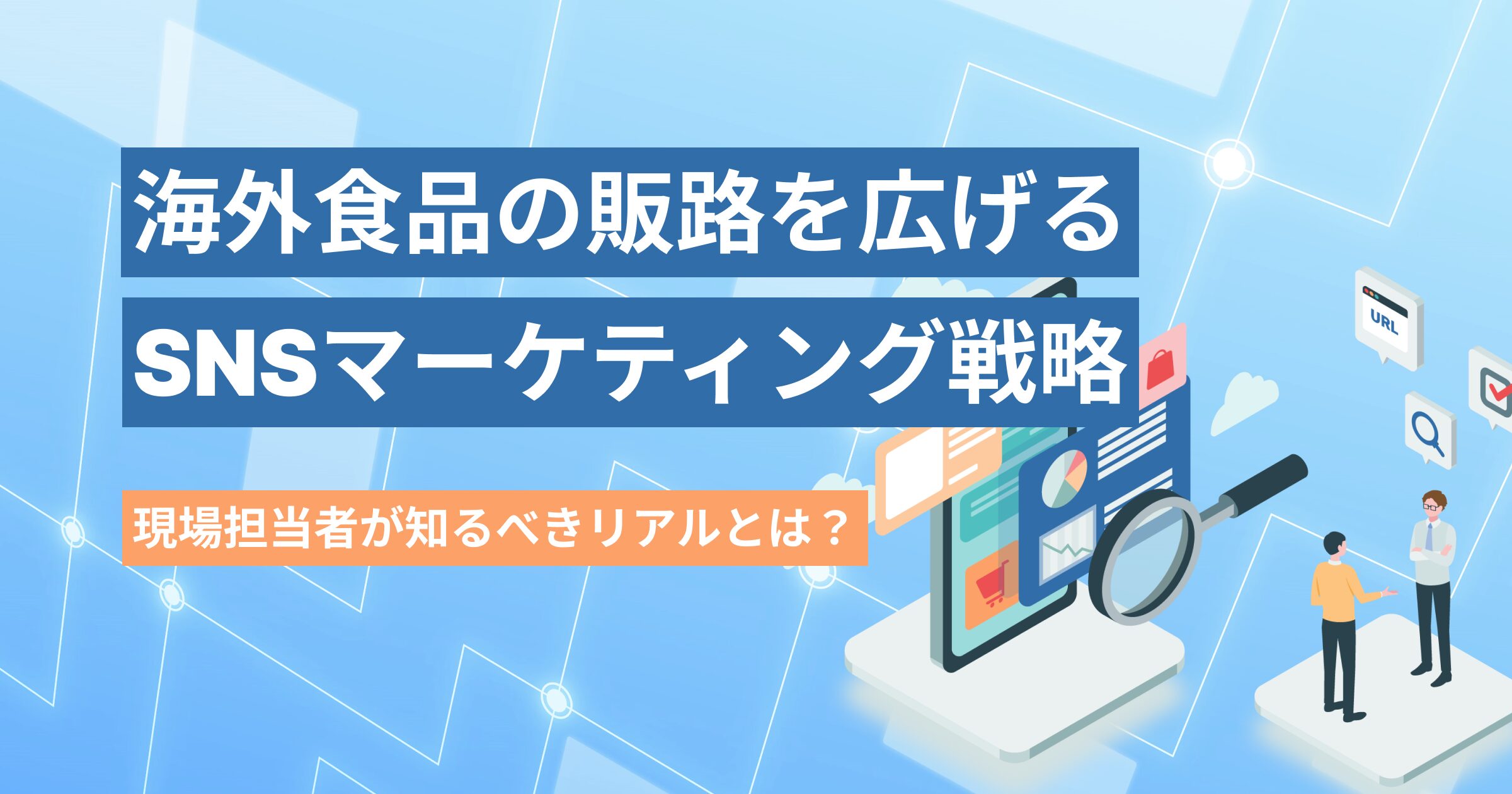
海外の消費者に自社の食品を届けたい。
そう思ったとき、最初に頭に浮かぶのは展示会や商社とのつながりかもしれません。
しかし、近年はSNSをきっかけに人気が広がり、現地のバイヤーや小売店から声がかかるケースが増えています。
とはいえ海外食品の販路を広げるためにSNSマーケティングをやれと言われても、何から手をつければよいのか迷う担当者は少なくありません。
この記事では、海外食品の販路を広げたい現場担当者のために、国別のSNS事情や消費者に刺さる発信の型、そして売上につなげるための具体的な視点を紹介します。
SNSで海外食品を売る現場担当者のリアルな壁
海外食品をSNSで広めようとしても、最初に直面するのは「何をどう始めるか」という壁です。
ここでは現場担当者が抱える代表的な課題と、その解決の方向性を整理します。
展示会頼みから脱却できない会社の事情
海外販路の開拓といえば展示会。
その流れはいまだに根強く残っています。
ただし展示会は出展費用が大きく、成果が数件の名刺交換に終わることも珍しくありません。
このままでは投資対効果が見合わず、SNSを取り入れる必要性が増しています。
解決策は「展示会で伝えてきた内容をSNSに翻訳する」ことです。
例えば試食で好評だった料理をレシピ動画にする。
ブースで話していた商品の由来を、現地言語で短く紹介する。
従来の強みをSNSに移す形なら、会社の理解も得やすく第一歩を踏み出しやすくなります。
「とりあえずSNSをやれ」と言われた担当者の孤独
社内から突然「SNSで海外に売れるようにしてくれ」と指示されることもあります。
しかし、媒体選びや成果指標を一人で考えるのは容易ではありません。
まずは「フォロワー数を増やすことを目的にしない」ことが重要です。
目的はあくまで商談や問い合わせにつながる行動です。
具体的には次の流れを意識すると良いでしょう。
- 国ごとに注力するSNS選び、集中して運用する
- 投稿には必ず購入先や問い合わせ窓口を明記する
- 成果報告は「いいね数」ではなく「問い合わせ件数」「現地からのDM数」にする
この方法なら、社内の理解も得やすく、担当者の孤独感も薄まります。
国ごとに違うSNS事情を知る
海外食品のSNSマーケティングでは、国ごとに使われるSNSが異なります。
対象国の特性を理解しておかないと、発信が届かず無駄な労力になってしまいます。
台湾・香港:InstagramとFacebookで“映える和”が強い
台湾や香港ではInstagramとFacebookが今でも強い影響力を持っています。
特に日本食品は「映える和」として人気が高く、写真映えする商品は拡散されやすい傾向にあります。
例として抹茶スイーツや和菓子。
現地インフルエンサーと組み、写真と体験談をセットで投稿することで、ブランド認知が急速に広がります。
中国:微信・小紅書(RED)を外せない現実
中国では海外SNSが規制されているため、微信や小紅書の活用が必須です。
小紅書は口コミ色が強く、食品では「調理方法」「健康への影響」「実際の味」が重視されます。
解決策は現地ユーザーの声を活かすことです。
商品のレビューを投稿してもらい、それを企業アカウントでも拡散する。
広告よりも口コミとして広がる方が信頼を得やすくなります。
欧米:TikTokで「料理体験」をどう見せるか
欧米ではTikTokが食品分野でも強力です。
ただ商品の説明をするだけではなく、現地食卓に取り入れる様子を短尺で表現するのが効果的です。
例えば「日本のだしパックを使ったスープ」や「抹茶のヘルシーデザート」。
調理の手軽さや新しさを体験型で見せることで拡散力が高まります。
台湾でブラックサンダーがSNSで大ヒットした理由
台湾でブラックサンダーが社会現象級のヒットになった背景には、複数の要因が重なっています。
SNSでの拡散だけでなく、商品の特性・社会的な出来事・小売の動きが組み合わさり、短期間で爆発的に広がりました。
要因・効果・学びの整理
| 要因 | 効果 | 学び |
| 2013年「ビッグサンダー」発売 | 食べ応え・コスパの良さがSNSで話題化 | 商品特性が「投稿したくなるネタ」になることが重要 |
| 2014年に日本生産量の約6割を台湾へ輸出 | 店頭欠品が続き「どこで買えるか」がSNSで拡散 | 欠品や再入荷も生活者にとっては拡散ネタになる |
| 7-ELEVENが130万本の緊急配荷を告知 | 入荷情報そのものが購買行動を促進 | 小売の公式発信をSNS拡散の起点にできる |
| ひまわり学生運動との偶然の結びつき | 運動のシンボルカラー「黒」とリンクし、差し入れで注目 | 社会的文脈や偶然の要素も話題を増幅する |
| 手頃な価格とボリューム感 | 子どもから大人まで幅広く消費され国民食化 | 価格・味・量感がSNSバズ後の定着を支える土台になる |
SNSの投稿と社会現象が火をつけた
当初のきっかけは「食べ応えのある新商品」としての評価でした。
しかし2014年には欠品が相次ぎ、「どこで買えるか」がSNSでシェアされることで一気に話題化。
さらに7-ELEVENの大規模な増産・配荷情報そのものがニュースになり、SNSで拡散されることで購買行動を後押ししました。
偶然も重なりました。
同年のひまわり学生運動では「黒」が象徴カラーとなり、差し入れとしてブラックサンダーが注目を集めたのです。
これにより「社会的な出来事」と「商品」が結びつき、単なる菓子以上の存在として語られるようになりました。
食品ブランドが学べる3つの視点
この事例から食品ブランドが学べるのは、次の3点です。
- 欠品や再入荷といった供給情報も、SNSでの強力なコンテンツになる
- 小売との連動は拡散力を何倍にも高める
- 社会や文化的な出来事を巻き込めば、商品は単なる「モノ」から「現象」になる
ブラックサンダーの台湾事例は、SNS・小売・生活者・社会現象が複雑に絡み合い、短期間で国民的菓子へと押し上げられた象徴的なケースです。
海外消費者に響く食品コンテンツの型
SNSに投稿するコンテンツは、ただ情報を並べるだけでは響きません。
海外消費者に刺さる3つの切り口を押さえておくと、発信の軸が明確になります。
「健康」「伝統」「体験」、3つの切り口で語る
食品の魅力は以下の3方向に整理できます。
- 健康:低カロリー・発酵食品・自然志向
- 伝統:和食文化・職人技・季節感
- 体験:現地にはない新しい調理体験
自社商品がどの切り口で語れるのかを明確にすると、発信がぶれません。
写真ではなく動画が主戦場になる理由
SNSのアルゴリズムは動画を優遇しています。
食品は特に「調理」「食べる瞬間」で魅力が伝わりやすく、写真より効果的です。
例:
- だしを使った料理の湯気
- 抹茶を点てる所作
- 箸で割った瞬間に広がる中身
視覚と感覚に訴える映像は、海外ユーザーの理解を一気に深めます。
翻訳ではなく「現地目線」での言葉選び
直訳は誤解を生みやすいです。
「だし」を単純にBrothとすると違和感が出ることがあります。
現地消費者に馴染みのある言葉を探すことがポイントです。
現地の料理に置き換えたり、調理例を示したりして伝わりやすさを重視しましょう。
フォロワー数より取引に近づく指標
SNSの数値はわかりやすいですが、本当に大切なのは取引につながる指標です。
担当者が迷わず動けるように、成果の見方を変える必要があります。
「いいね」よりも「問合せ数」を見える化する
フォロワーやいいねは参考指標に過ぎません。
重要なのは問い合わせや資料請求など、次の行動に直結する数値です。
フォームやDMでの連絡件数をKPIに設定することで、SNS運用の社内評価も納得感が増します。
SNS広告と組み合わせて商談を作る方法
自然投稿だけではリーチが限られます。
そこで有効なのが広告活用です。
ターゲットを「台湾の20代女性・健康志向」と細かく設定できるため、効率よく潜在顧客に接触できます。
さらに広告経由のリードを展示会やオンライン商談につなげる導線を整えると、成果に直結します。
現場担当者がすぐに動ける3ステップ
理論を知っても、動けなければ意味がありません。
担当者が実務で始められる3ステップを紹介します。
まずは国ごとにSNS選択を絞り込む
複数のSNSに手を出す必要はありません。
まずはターゲット国で利用率の高いSNSを一つ選び、集中的に運用します。
自社商品の「伝わる切り口」を決める
商品の魅力を「健康・伝統・体験」のどこで伝えるのかを決めます。
例えば抹茶なら「健康と伝統」、だしなら「健康と体験」。
こう整理すると、発信の一貫性が出ます。
指標とKPIを小さく設定して試す
最初から大きな目標を掲げると挫折しやすいです。
「1か月で問い合わせ3件」など小さなKPIを設定し、成果を積み上げることが重要です。
SNSだけでは届かない壁を越える方法
SNSは万能ではありません。
取引に直結させるには他の施策と組み合わせることが必要です。
現地パートナーと連動した発信の強さ
現地の小売店や輸入業者と連携することで、SNS発信の信頼度は一気に高まります。
「現地で買える」という安心感が生まれるからです。
共同投稿やタグ付けで現地発信を巻き込むと効果的です。
SNS→展示会→商談へつなぐ導線設計
SNSは認知の入り口です。
そこから展示会やオンライン試食会につなぎ、商談でクロージングする流れを意識しましょう。
SNS単独では売上に直結しにくいですが、導線を描くことで販路拡大の仕組みに変わります。
まとめ
海外食品の販路をSNSで広げる動きは加速しています。
しかし、担当者が抱える課題は国ごとの事情や社内環境によって異なります。
- 国ごとにSNSを選定する
- 消費者に響く切り口で発信する
- 成果は問い合わせや商談で測定する
この3つを押さえれば、SNSは「やらされ業務」から「成果を生む武器」へと変わります。
現場担当者が一歩踏み出すことで、海外食品ビジネスの未来は大きく広がっていくはずです。
とはいえ、SNSだけで販路を切り開くのは簡単ではありません。
信頼や販売実績を築くには、百貨店の催事出展などオフラインの場も非常に魅力的です。
実際に現地消費者が商品を手に取り、味わい、購入する体験は、SNSでは得られない効果を持ちます。東西食品では、台湾をはじめとしたアジアの大手百貨店への出展支援を数多く行っています。
200件以上の実績をもとに、SNS発信と現地催事を組み合わせた販路拡大をサポートします。
海外展開を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
