お役立ちコラム
小規模食品メーカーが海外輸出で年商を飛躍的に伸ばす具体的なステップ|越境EC・百貨店フェア・物流コスト徹底比較
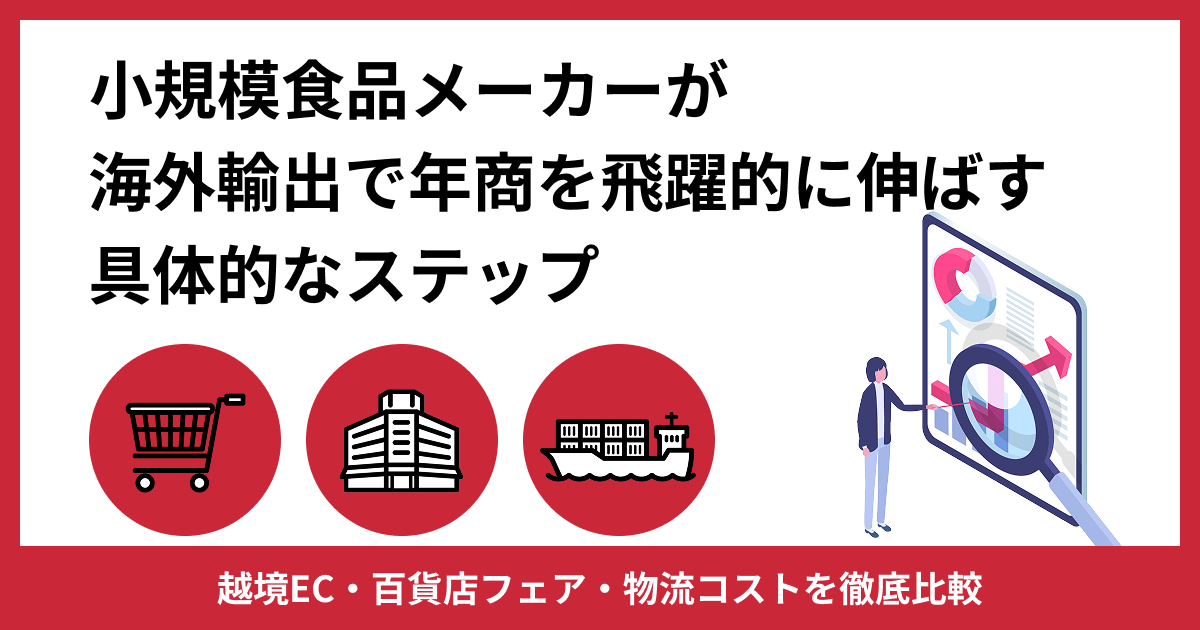
国内での販路に限界を感じはじめた小規模食品メーカーが、いま注目しているのが「輸出による販路拡大」。
かつては商社に頼るしかなかった海外展開も、現在では越境ECや共同出荷サービスの発展により、少ない投資でもチャレンジできる時代になりました。
本記事では、小ロット輸出からスタートし、年商UPを海外で実現するための具体的な方法を紹介します。越境EC・3PL・百貨店フェアなど4つのモデル比較から、国別の規制、通関フロー、初期費用の相場まで、小規模事業者に必要な情報を解説します。
小ロット輸出が現実解になる背景と市場規模
「輸出」と聞くと、大手メーカーや商社の話のように感じる方もいるかもしれません。
しかし、ここ数年で物流インフラや販路の仕組みが大きく変わり、社員10名以下の小さなメーカーでも海外展開が現実的な選択肢になりつつあります。
国内売上が頭打ちになる理由
地方の道の駅、地場スーパー、地域催事。
地域に根ざした販売チャネルは、安定した売上を支えてくれますが、どうしても規模に限界があります。人口減少が進む地方では、これまで通りの販売活動だけでは売上を維持することさえ困難です。
一方で、地元の素材を活かした加工食品は「日本らしさ」の象徴として、海外市場で高く評価されることも少なくありません。まさに今が、次の一手を考えるタイミングです。
日本食品の輸出伸長データ
農林水産省の発表によると、2023年の農林水産物・食品の輸出額は1兆4,000億円を突破。10年前の約2倍という成長を見せています。特にアジア圏では、日本産食品への需要が根強く、現地バイヤーによる仕入れ意欲も高まっています。
中でも人気なのは、以下のようなカテゴリです。
- 常温で保存可能な加工食品(ドレッシング、レトルト食品など)
- 見た目が美しいお菓子や調味料(ギフト需要が高い)
- 地域性が感じられる商品(地名入り、ストーリー性あり)
小規模企業が参入しやすい条件
海外展開といっても、すべてを自社で担う必要はありません。以下のような支援インフラが整備されているため、参入ハードルは年々下がっています。
- 越境ECプラットフォーム(Amazon、Shopee など)
- 複数企業による共同物流サービス(小ロット対応)
- 海外百貨店の日本フェアなどの合同出展枠
- ラベル翻訳や書類作成の専門業者
- 各種補助金・助成金制度
こうした外部リソースを活用すれば、初期費用を抑えつつ海外販路を開拓できます。つまり、社員10名以下の加工食品メーカーでも、十分に戦える時代なのです。
需要・規制・物流コストで絞るターゲット国早見表
輸出を始めるにあたって、まず最初に考えるべきは「どの国をターゲットにするか」です。食品輸出では、需要があるだけでなく、現地の規制や物流コストとのバランスを取ることが欠かせません。
消費規模と関税率の一覧
以下は、2025年時点で日本産食品の主要輸出先となっている国・地域を、需要規模と関税率の観点から比較した一覧です。
| 国・地域 | 日本食品の人気度 | 関税率の目安 | コメント |
| 台湾 | 高い | 比較的高め。多くが15%~30% 一部10%以下もある | 親日性が高く、食品フェアの開催も多い |
| 香港 | 高い | ほぼゼロ | 高級品需要が強く、百貨店と相性がよい |
| シンガポール | 中〜高 | ゼロ(酒類など特定品目を除き無税) | 富裕層向けのギフト需要あり |
| アメリカ | 中〜高 | 品目による | 表示義務や成分規制が厳しい点に注意 |
| 中国(本土) | 中〜高 | 比較的高め | 通関に時間がかかる傾向がある |
このように、同じアジア圏でも「通関のしやすさ」や「販路の確保のしやすさ」には差があります。
最初の一歩としては、台湾や香港のように、規制が緩やかで日本食品の受け入れに慣れている国が適しています。
運賃・リードタイムの目安
輸出では、距離だけでなく、通関の複雑さ・物流手段の選択肢が納期とコストに影響します。
以下に主要国への配送目安をまとめました。
| 国・地域 | 航空便リードタイム | 船便(LCL)リードタイム | 通関における検査日数 |
| 台湾 | 1〜3日 | 約1週間 | 台湾の通関にかかる日数は航空便で1~2週間船便で3~6週間 |
| 香港 | 1〜3日 | 約1週間 | 香港の通関にかかる日数は航空便で1~3日船便で3~7日 |
| シンガポール | 1〜3日 | 約10日〜2週間 | シンガポールの通関にかかる日数は航空便で3~10日船便で1~2週間 |
| アメリカ | 3〜5日 | 約1か月 | 通関に時間がかかるケースあり |
リードタイムが短い=鮮度維持がしやすく、在庫リスクも抑えられるため、はじめの輸出先としてはやはり台湾や香港が現実的といえます。
4つの販路モデルとコスト比較
輸出を検討する際、どの販路モデルを選ぶかは戦略の分かれ道です。
ここでは、初期費用や粗利率などの観点から、主要な4つの販路モデルを比較していきます。
越境EC+FBA
AmazonやShopeeなどを活用した越境ECでは、販売ページの作成や広告運用の知識が必要になるものの、自社主導でブランドを育てられるという利点があります。
FBA(フルフィルメント by Amazon)を活用すれば、現地倉庫からの出荷も可能です。
【主な特徴】
- 初期費用:約50万円(翻訳・ページ作成・広告含む)
- 出荷:FBA倉庫 or 現地在庫配送
- 粗利率:60〜70%目標可能
- デメリット:返品対応や顧客対応が手間
個人経営〜従業員5名以下の企業でも対応しやすく、輸出の入り口としては有力です。
共同3PL出荷
最近注目を集めているのが、複数企業で出荷スペースを共有する「共同3PL」モデルです。
MOQ(最小ロット)は100kg程度から受け入れ可能で、保管・通関・現地配送まで一貫対応してくれる会社もあります。
【主な特徴】
- 初期費用:30〜60万円
- 出荷:月1便〜2便の混載船・航空便
- 粗利率:50〜60%前後
- デメリット:SKUや日程に制限あり
コストを抑えて、百貨店や商業施設でのテスト販売と連携できるケースもあります。
商社・代理店委託
海外とのやり取りに不安がある事業者にとって、商社や代理店への委託は安心感があります。
一方で、手数料がかかることや、商流を握れない点はネックです。
【主な特徴】
- 初期費用:10万円程度(営業資料など)
- 出荷:代理店または現地法人経由
- 粗利率:30〜40%になるケースも
- デメリット:販促や売価をコントロールできない
ブランディングや販促戦略にこだわりたい場合は、慎重な判断が必要です。
海外百貨店日本フェア
「短期で反応を見たい」「現地の声を直接聞きたい」というニーズに応えるのが、日本食フェアのような期間限定イベントへの出展です。
実際に買ってもらいながら、現地での温度感や購買導線を把握できます。
【主な特徴】
- 初期費用:100万円(ブース装飾・渡航費・販促物込み)
- 出荷:主催者による取りまとめ or 直接搬入
- 粗利率:イベント販売+事後販路展開に期待
- メリット:現地バイヤーと直接交渉ができる/テストマーケティング効果が高い
初回出荷を成功させる物流と通関5ステップ
販路やターゲット国が決まったら、次はいよいよ出荷の準備です。
物流や通関のプロセスを理解し、抜け漏れなく進めることが、初回輸出の成否を大きく左右します。
以下に、小規模事業者でも実行可能なフローを5つのステップにまとめました。
成分証明・HSコード確定
最初に行うべきは、商品に含まれるすべての原材料や成分の明記です。
輸出時には、各国ごとの関税分類である「HSコード(Harmonized System Code)」の申告が求められます。
そのためには、以下の情報が必要になります。
- 原材料の一覧
- 加工工程の説明
- 成分表示や栄養成分表
これらを基に、税関または通関業者が該当するHSコードを確定してくれます。
申告ミスがあると、税率の間違いや通関トラブルにつながるため注意が必要です。
ラベル・翻訳・包装
続いて、商品ラベルの現地対応です。
国によっては、現地語で以下のような情報の記載が義務付けられています。
- 商品名
- 原産国
- 賞味期限・保存方法
- アレルゲン表示
- 栄養成分表示
ラベルは印刷だけでなく、現地語への翻訳+パッケージ貼付の作業費も必要です。
小ロットで対応可能な業者も増えているため、早めに見積もりを取ると安心です。
混載・温度帯・保険手配
物流手段は、以下の3パターンに分かれます。
- 航空便(高コスト・短納期)
- 船便LCL(混載、低コスト)
- クール便・冷凍便(追加料金)
100kg〜200kg程度であれば、『他社とスペースを共有する「混載便(LCL)」』の活用がおすすめです。
また、輸送中の破損・温度逸脱などに備えて、貨物保険の加入も忘れずに。
通関書類とリードタイム
通関には、以下のような書類が求められます。
- インボイス(送り状)
- パッキングリスト
- 輸出入許可証(必要な場合)
- 成分証明書や衛生証明(食品の場合)
- 製造工程表
通関書類の不備は出荷遅延の原因となるため、信頼できる通関業者に相談しながら進めると安心です。
出荷後の品質トラッキング
輸出後も、納品確認や在庫状況の把握は欠かせません。
近年は、リアルタイムで温度・位置を把握できるロガーや、現地での商品陳列状況を撮影するレポートサービスなども普及しています。
出して終わりではなく、「売れたか・残ったか・どこで差が出たか」を振り返る体制を整えておくことが、リピート販路づくりの鍵になります。
国別ラベル・アレルゲン要件チェックリスト
輸出において、ラベルのルールは国によって大きく異なります。
一律ではなく、「ターゲット国にあわせた表示対応」が必須です。
ここでは主要な3つの地域について、要件の傾向を整理しました。
北米向け必須表示
アメリカやカナダでは、FDA(米国食品医薬品局)などの規制により、栄養成分やアレルゲンの詳細表示が義務付けられています。
特に下記の情報は明記が必要です。
- 熱量(kcal)
- 食塩相当量
- トランス脂肪酸含有量
- アレルゲン(卵・乳・小麦など)
また、表示言語は基本的に「英語」ですが、カナダでは「英語+フランス語」の併記が求められる場合があります。
香港・台湾向け繁体字表示
香港・台湾は、親日で日本食品の流通が盛んな地域です。
一方で、食品安全の観点から、以下の情報を「繁体字」で表示する必要があります。
- 賞味期限(年月日の順)
- 原産地(例:日本國)
- 保存条件(常温/冷蔵/冷凍)
シール対応も可能ですが、商品1つずつに貼付が必要になるため、外注コストと手間を考慮しましょう。
ASEAN向けハラル・成分規制
マレーシア・インドネシアなどのイスラム圏では、ハラル認証の取得が販路開拓のカギになります。
また、ASEAN各国では特定の添加物や着色料に制限があるため、以下の点に注意が必要です。
- 豚由来成分・アルコール含有の有無
- 認可された添加物一覧との照合
- 成分翻訳の正確性
現地のパートナーや検査機関と連携しながら、ラベル表示を詰めていきましょう。
海外百貨店フェアに参加した場合のシミュレーション
最後に、海外百貨店の日本フェア出展を想定した小規模メーカーのシミュレーションを紹介します。
年間売上1億円未満の企業でも、投資100万円で海外比率を15%に伸ばす例です。
プロジェクト概要と12か月タイムライン
【輸出スケジュールの全体像】
| 月 | 活動内容 |
| 1か月目 | 出展決定・商品選定・現地リサーチ開始 |
| 2か月目 | パッケージ・ラベル改訂、販促物制作 |
| 3か月目 | 通関手配・現地倉庫配送手続き |
| 4か月目 | フェア出展(7日間)+バイヤー商談 |
| 5か月目以降 | SNS強化+越境EC連携でリピート促進 |
総投資100万円の費用内訳
【費用内訳の目安(概算)】
- 出展料・現地装飾費:約20~30万円
- 通関・物流費:約10~30万円
- 渡航費・宿泊費:約20万円
- 販促物制作・広告・人件費:約10万円
- その他(保険・予備費):約10万円
合計:約70万円~100万円
このうち、約50万円は補助金でカバーできる可能性があります。
実質の持ち出しは20万円~50万円程度となります。
まとめ
小規模な食品メーカーにとって、海外輸出はもはや遠い世界の話ではありません。
物流や通関のハードルは確かにありますが、越境ECや百貨店フェア、共同3PLといった手段を選べば、初期投資少額からでもスタートできます。
この記事では、輸出国の選び方から4つの販路モデル、通関フロー、ラベル規制、そしてリアルな成功事例まで紹介してきました。
現地での反応を確かめながら、小ロットから始めることで、低リスク・高実感の第一歩が踏み出せます。迷ったときは、ひとりで抱え込まずに、専門家や伴走支援企業に相談してみてください。
自社の強みを海外へ届ける挑戦が、新しい販路と価値を切り拓くきっかけになるはずです。
有限会社東西食品は、アジアへの出店支援多数ではじめて海外進出を検討する企業のサポートを数多く行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
